それは、大きな緑色の石が乗った、おもちゃみたいな指輪だった。
 「結月も何か欲しいものはないか?」と叔父から電話がかかってきたのは、かれこれ5年前のことだった。祖母の家が取り壊されることになり家財道具を整理していたのだろう。結月は、幼稚園の入学式で配るお便りを作り終えると祖母の家まで車を走らせた。特にほしいものはないが、もう一度あの家を見ておきたいと思ったからだ。慣れ親しんだ山道を登り辿り着いた場所は、祖父が大事に育てていた木々が伐採され既に知らない家のようだった。
「結月も何か欲しいものはないか?」と叔父から電話がかかってきたのは、かれこれ5年前のことだった。祖母の家が取り壊されることになり家財道具を整理していたのだろう。結月は、幼稚園の入学式で配るお便りを作り終えると祖母の家まで車を走らせた。特にほしいものはないが、もう一度あの家を見ておきたいと思ったからだ。慣れ親しんだ山道を登り辿り着いた場所は、祖父が大事に育てていた木々が伐採され既に知らない家のようだった。
それでも玄関を開けて、「こんにちは」と言うと祖母の返事が返ってきそうだ。物が散乱した部屋の中を注意深く歩いていった。花札やトランプ、飴の入った瓶も床に転がっている。子どもの頃憧れだったこの家の全ての魔法が解けてしまっていた。大きな桐の箪笥も、大理石の応接セットも必要なかった。結月は、家を一周したあと、ずっと昔から祖母の日用品を入れていた黄色に花柄の小さな整理箪笥がほしいと言った。
「こんな古い箪笥でいいのか?」と言いながら叔父の顔はほっとしていた。きっと既に着物やテーブルは引き取り手が決まっていたのだろう。立て付けの悪い引き出しを開けると、おばあちゃんの懐かしい匂いがして、思わず涙が出そうだった。一番上の引き出しから見慣れたカラフルな包装紙が出てきた。しかも山のように。
「あ、これ! おばあちゃん、デパートの包み紙ためてたやつだ。ちらし寿司なんか作って持たせてくれるときに、ここから包装紙を出してパックを綺麗に包んでくれたんだよ」
へー。食器を分類しながら叔父は興味なさそうに返事をした。箪笥は自分の乗用車に積んで帰れそうだったので、結月は足早に立ち去り、そのまま一人暮らしを始めたばっかりのアパートに持ち帰った。
 「それで? それで、この指輪はどうしたってのよ!?」
「それで? それで、この指輪はどうしたってのよ!?」
妹の真由華がマシンガンみたいに問い詰めてくる。
「だから、引き出しの一番上に入ってたの」
「桐の箪笥じゃなくて? デパートの包み紙が入ってたこのおんぼろの引き出しに?」
「うん。そのまま包装紙も入れたまま持って帰ってね……」
「それで5年間、指輪に気づかなかったの? うそだー、お姉ちゃん指輪があるの知ってて持って帰ったね??」
にやにやしながら真由華がけしかける。
「違うよ。本当に昨日気づいたんだよ」
「にしてもでっかい石。絶対高いよね、これ」
真由華が右手の中指にその緑の大きな石がついた指輪を入れてみると、ぶかぶかで、親指に入れてもまだ緩かった。
戦中に高校時代を送った祖母は、戦地に行って男手のない農家へ、勤労奉仕として手伝いに行っていたのだと聞いたことがある。勉強ひとつさせてもらえず朝から晩まで外で働いたから顔はシミだらけに、指はじいちゃんより太くなったのよなんて笑ってたっけ。
「お姉ちゃん! これさ、翡翠だよ。この大きさだと80万くらいだって!」
 スマホをいじりながら真由華が叫んだ。
スマホをいじりながら真由華が叫んだ。
「へー。すごいんだねえ」
「ねえ、確か私が高校生のときさ、おばあちゃん指輪がないないって探してなかった?」
「あー、確かにそうだったかもねえ」
「絶対そうだよ。この緑色の指輪、結婚指輪の代わりにってずっとしてたやつだよ」
こういうことだけは真由華はよく憶えているのだ。確かにそうだ。結婚のときに大した指輪を買ってあげられなかったからって、おじいちゃんが後で買ってくれたんだと目を細めて何度も話していた気がする。それを何だって包装紙と一緒にしまい込んでしまったのだろう。
「ばあちゃんさ、ずぼらなとこあったじゃん? 冷蔵庫の中もぐちゃぐちゃだったしさ、お年玉も開けてみたら空っぽだったりさ」
「確かにね、この指輪もきっと何かの拍子にここに入れたまま忘れちゃったんだね」
アーモンドほどの大きさの緑の石は、豪華すぎてぱっと見おもちゃの飴みたいに見えた。銀婚式か何かの記念に祖父が渡したものだろう。ノートも消しゴムも鉛筆も祖父母の家はいつも引き出しいっぱいに買い置きがあって行く度にもらうのに、またいつの間にか増えていた。今思えば病的なまでのストック量だった。「おばあちゃんは若い頃、買いたくても物がなかったからね、今は好きなだけ買いたいの。物に囲まれていたいのよ」と笑って言う祖母の言葉には、誰も責められない切なさがあった。
指輪を叔父さんに返した方がいいのかなと一瞬思ったけど、黙っていればわからないよと真由華が言うので、また引き出しの中にしまった。
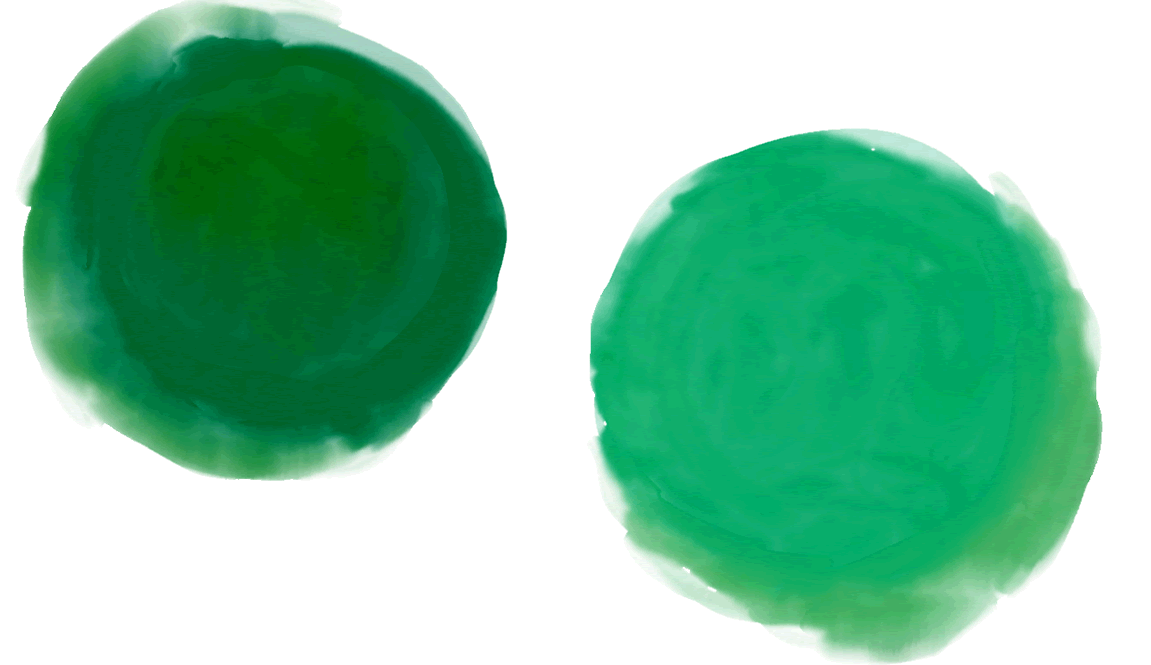
深夜にインターホンが鳴った。入ってくるなり、「疲れたー」と俊介がソファーに崩れ落ちる。きっと彼の仕事は順調だ。順調に忙しいのだから喜ばしいことだ。落ち着いたらねと言いながら、いつになったら一緒に暮らすことになるのだろう。
ビーフシチューを温めながら、追い焚きのスイッチを押す。俊介は今にもそこで寝てしまいそうにうとうとしていて、そっとブランケットをかけて、また追い焚き停止のボタンを押す。このままずるずると生活は続いていくのだろうか。どこかにもっといい男が落っこちているわよと真由華は言うけれど、結月には俊介しか考えられなかった。どうしてかと言われると言葉に詰まってしまうが、この黄色い整理ダンスを愛するようにずっと愛していける自信があった。「お姉ちゃんは欲がなさすぎるよ」なんて言うけど、本当は誰より強欲だ。今すぐプロポーズしてほしい、薬指に入れる指輪が欲しい、結婚したい。しかもそれが誰でもいいわけでなく、目の前に横たわるこの眼鏡のずれた男でないといけないのだから。
結月は引き出しの中から緑の指輪を取り出し、若かりし日の祖父母のことを考えた。約60年という歳月を一緒に歩くことになるのだと、そんなことはきっと想像さえしなかったのかもしれない。指輪は蛍光灯に照らされて、長い眠りから覚めたようにゆらゆらと輝いていた。
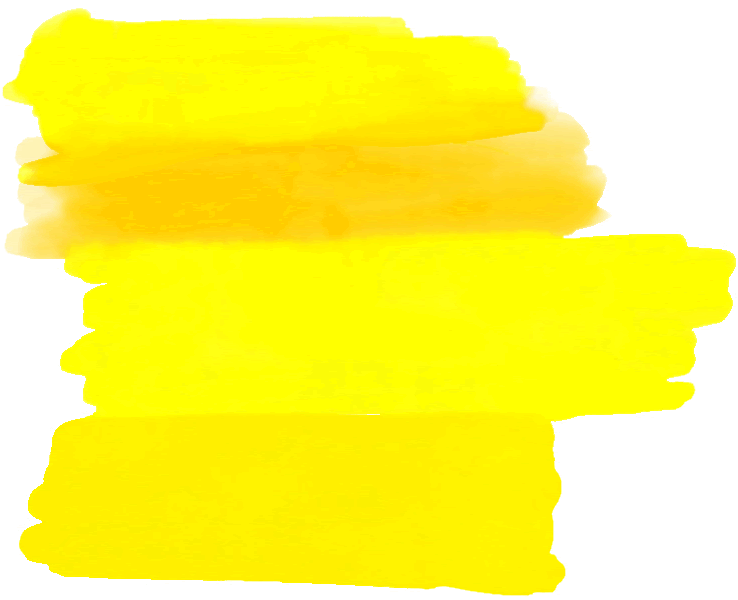
翌日、幼稚園から帰ったあと、結月は真由華に電話をかけた。
「あの指輪、まゆちゃんにあげるよ。ほしいんでしょう。でも売ったりしちゃダメよ?」
「ちょっと、私も今電話しようと思ってたところ。あのね、その指輪……偽物なんだって」
真由華が神妙な声で告げた。
「ええ? どういうこと?」
「さっき気になって母さんに電話で聞いたのよ。したらね、あれ翡翠じゃないんだって。
だからさ、お姉ちゃん、おばあちゃんの形見だと思って大事にとっておきな。ね!」
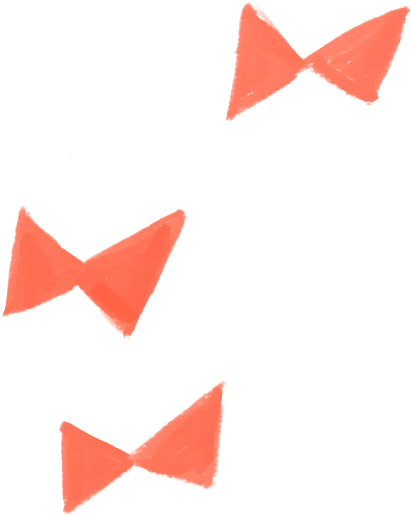 言いながら真由華はくすくすと笑いだした。結月もなんだか可笑しくて声を上げて笑ってしまった。そうこうしていると、今日は仕事が早く終わったのか、俊介がちゃんと合鍵で入ってきた。笑っている結月を見てつられたのか俊介も笑いはじめた。
言いながら真由華はくすくすと笑いだした。結月もなんだか可笑しくて声を上げて笑ってしまった。そうこうしていると、今日は仕事が早く終わったのか、俊介がちゃんと合鍵で入ってきた。笑っている結月を見てつられたのか俊介も笑いはじめた。
電話を切ると、「楽しそうだね?」と聞いてくるので、ここまでの指輪物語を俊介にも話した。翡翠の指輪を買ったあと、じいちゃんは事業に失敗してしまったらしい。家中のジュエリーや着物を質に入れてばあちゃんは何とか母さんたちを育てたそうだ。そして、じいちゃんが買ってくれたのと似たような緑色の樹脂の指輪を買って、ずっとしていたのだそうだ。じいちゃんは、それを死ぬまで知ることはなかったって。
「偽物だけど、本物だったってことだね」
俊介が言った。同じことを思える人がすぐ傍にいることが幸せだと思った。
「僕らもそういう夫婦になれるといいね」
「嫌よ。私、指輪を質に入れたくないわ」
照れ笑いをしながら、素直になれない自分が憎らしかった。







